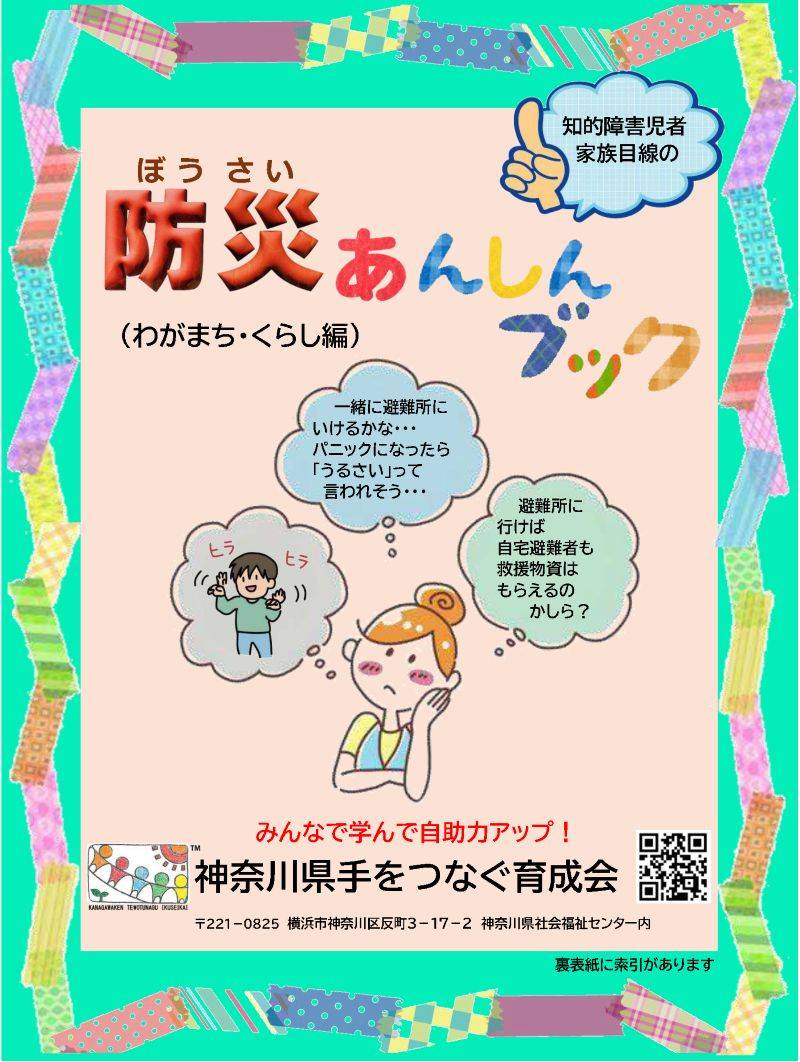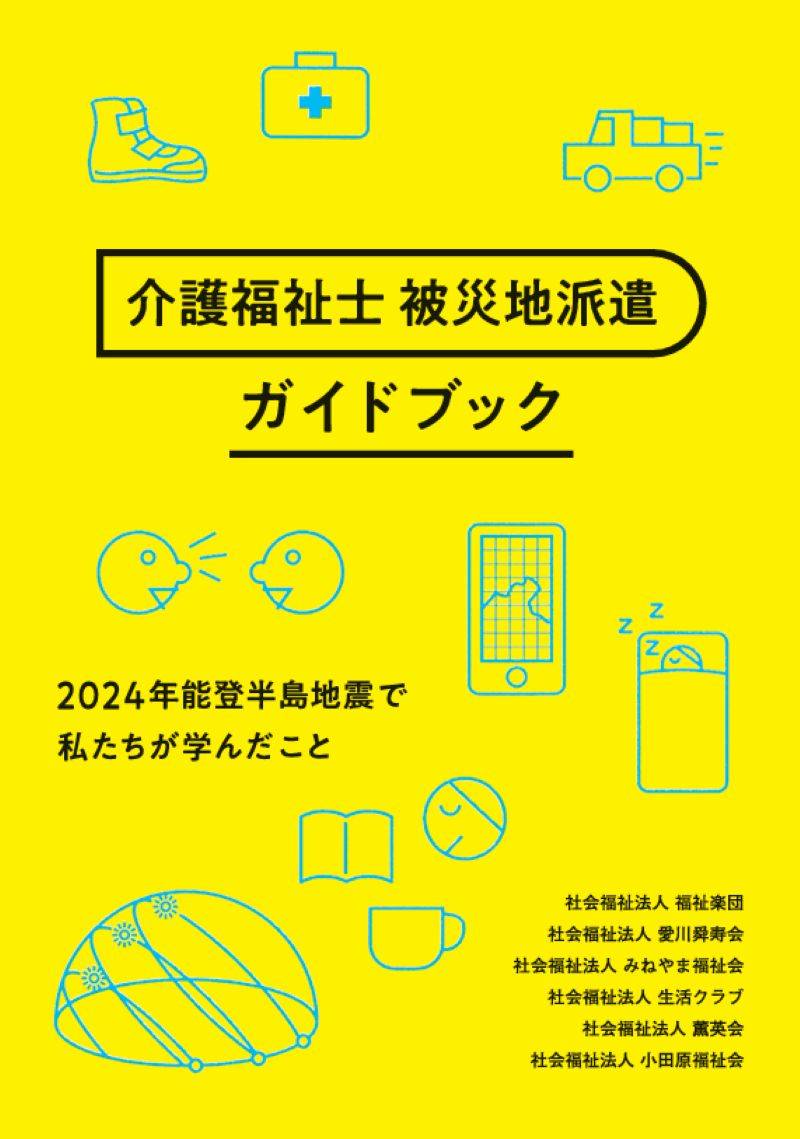【第3回】困難な課題を抱える女性と子どもへの支援の現状〜母子生活支援施設の現場から~
施設部会・母子生活支援施設協議会会長 諏訪部依子
- 分野 こども /
- エリア- /
- 推進主体 社会福祉法人・事業所 /

改正児童福祉法と「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(女性支援法)が令和6年4月に施行されます。改正児童福祉法の中では、困難を抱える妊産婦等への支援事業が創設され、女性支援法では包括的な支援を提供するための民間団体との多機関の連携・協働の体制づくり等、市町村における女性と子どもの福祉の充実が図られます。その推進に向けては、困難な状況にある女性や子どもの生活課題の共有化がより一層求められます。
今回は、女性や子どもの生活課題と支援の現状について、本会施設部会・母子生活支援施設協議会会長の諏訪部依子さんにお話を伺いました。
母子生活支援施設は児童福祉法に基づいた福祉施設です。原則18歳未満の子どもがいる母子世帯が、施設に入所しながら支援を受けて自立を目指します。利用者の主な年齢は10代から40代。利用の背景は、配偶者による家庭内暴力からの保護、住居や仕事がない生活困窮の状況など様々です。
県内には現在10カ所(横浜市8カ所・川崎市1カ所・相模原市1カ所)、各施設の定員は概ね20世帯。市町村の福祉事務所で申込み、契約により利用します。
利用者のこれまでの人生を強みに変えて、自立を目指す
施設での生活の風景から、職員はご本人の買い物やゴミの出し方、洗濯や掃除の様子、子どもへの接し方など、これまでの親子の暮らし方を知ります。親子の自立に向けてどのような生活支援が必要か。職員は日々、親子と顔を合わせ、日常生活の援助を行うことで把握します。
「入居に至るまでの間、頼る相手を求めて友人の家を転々としてきた、夫からの暴力に耐えてきた、病気や障害により仕事に就けなかったなど、ご本人は、自立するにも社会的に不利な状況に置かれてきました」と諏訪部さん。
ご本人から子ども時代の様子を聞くことができるようになると、今の生活と似たような過酷な環境に身を置いて育ってきたことを知ることもあります。
「ご本人の『生き抜いてきた』つらい体験を今後に向けての強みと理解し、ご本人にとって『信頼できる人』として関係を作ることが、支援者にとって欠かせません。入居されてから、職員が部屋の中に入れてもらえるまで1年ほどかかる方もいます。その方から『これまでの人生で褒められたことが無かった。安心して頼って良いんだと、ようやく思えた』と言われました。職員が応援する姿勢を示し続けることで、ご本人が元気を取り戻し、生活基盤を整える生活が始まります。そこからようやく、自立に向けて進むことができます」と続けます。
施設の利用期間は概ね2年から3年。ご本人と作成した支援計画に基づき、子育て、仕事、健康のことなど退居後の生活設計に向けて、必要な福祉・医療・法的なサービスの活用ができるように環境調整が図られます。施設の安心した環境の中で暮らす経験が、社会で生きる基盤となっていきます。

居室の広さは概ね2DK。地域での生活をイメージしながら生活基盤を整える
子ども自身が気持ちを伝え、望む暮らしをつくれるように
安定しない環境下で生活してきたのは子どもも同様です。子ども自身が生活する力を付ける支援も行われます。中には小学校高学年であっても、カップ麺のふたの開け方やお湯の沸かし方が分からない、おやつを買うにもお金の計算ができないこともあります。施設の学童保育では、お小遣いの使い方の勉強や、冷蔵庫にあるもので簡単なおかずを作るプログラムなど、子どもが日常生活で役立つ体験を増やしています。
また、諏訪部さんは職員と子どもの関わりの重要性について、「子どもたちにとって職員は、親とは違う大人との出会いです。次第に『こんなことをしてみたい』と思っていることや気持ちを話してくれるようになります。入居当初、子どもが親に対して意見を言う場面は少なく、一見『良い子』と思われるかもしれませんが、それは、暴力や暴言、貧困が日常下にあって、その環境から身を守るために、気持ちを出さないことを余儀なくされてきたからです。子どもがどんな生活を望んでいるのか、安心できる環境の中で、本当の気持ちを出せることが大事だと考えています」と話します。
親子の関係を支えるために、職員も同席した親子の「家族会議」を行う施設もあります。家族会議では子どものゲーム時間、寝る時間などの細かな決まりごとについて話し合います。親子だけでは感情的になりがちですが、お互いの言い分を伝え合い、改善策を考えていきます。親子で話し合いながら生活を作る経験は、退居後を見据えた生活にも活かされているようです。
家族を支える福祉施設として
さらに、施設では退居後の「アフターケア」として、仕事や子育ての様子を電話や訪問で把握したり、行事に誘うなど、子育ての地域資源として、継続的に関わる取り組みに力を入れています。また、支援が必要な妊娠期のひとり親に対して、施設を活用し、産前から産後まで切れ目のない支援を制度化している自治体もあります。
その一方で、母子生活支援施設には保育士や看護師の配置など、妊産婦支援に課題も残されています。さらに、施設が所在しない市町村には、困難な課題を抱える母子を支えるための支援策の一つとして、施設の活用に向けた対応策も期待されています。
諏訪部さんは「社会の中で孤立する家族が少なくない中で、母子の地域生活を支えるソーシャルワーク実践を行う母子生活支援施設の役割は、ますます必要になってくる。そのことを社会に伝えていきたい」と力強く語ってくださいました。(企画課)
退居時に寄せられた親子からのお手紙
入居された方から
入居当時、心身ともに疲弊し、疲れ切っていましたが、サポートのおかげで回復し、前進することができました。子育てに行き詰まったときに、私の事を否定せずに丁寧に向き合っていただけたことがすごく嬉しかったです。とても救いになりました。施設の時間は、私の大切な休息期間でした。人生の大きな分岐点だったと思います。落ち着いて自分自身を見つめなおす期間でした。大切な日々を忘れずに、前を向いて強く生きていきます。(抜粋)
子どもから
がくどうや、みんなで外であそんで楽しかったし、みんなでおにぎりやおもちを作って楽しかったし、たくさんの思いでができました(抜粋)