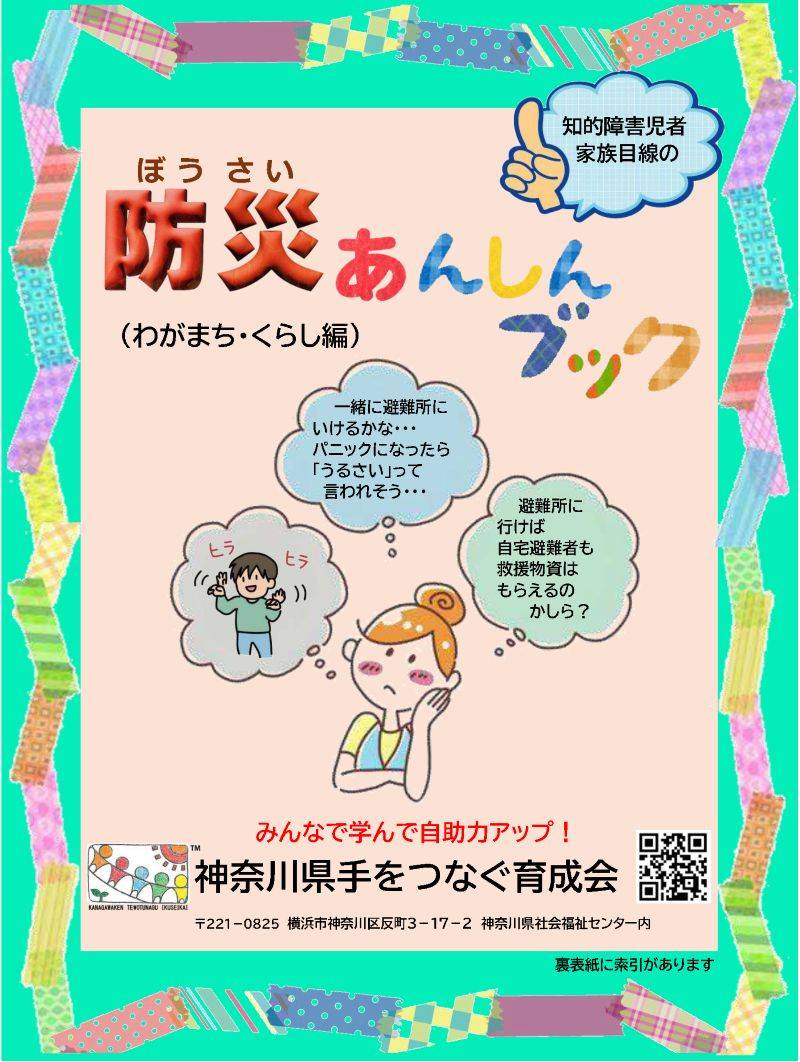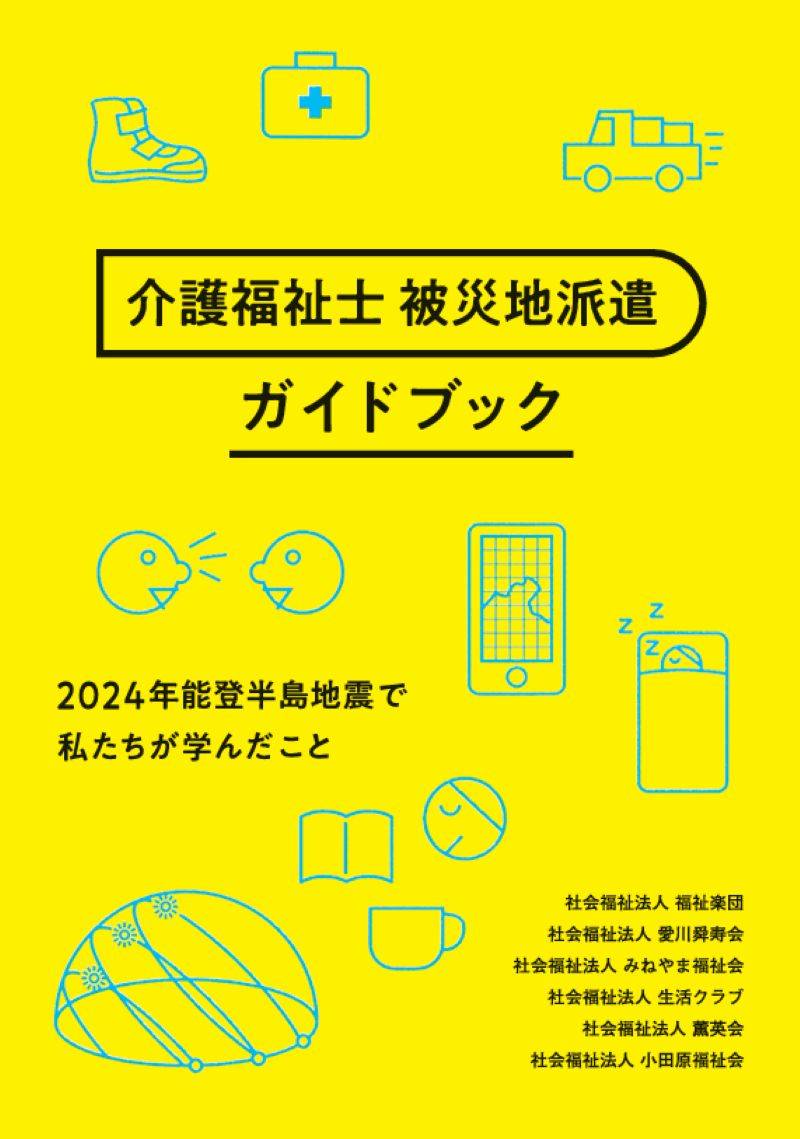災害時に誰ひとり取り残さない福祉を目指して
県地域福祉課災害福祉グループ
- 分野 地域 /
- エリア横浜市 /
- 推進主体 行政 /

はじめに
我が国では地震、風水害、大規模火災、噴火などさまざまな災害が発生しています。これまでの災害発生時には、高齢者、障がい者などの要配慮者の方々の逃げ遅れや、長期の避難生活を余儀なくされ、必要な支援が行われない結果、体調悪化や要介護度の重度化、最悪の場合には「災害関連死」といった二次被害が多く発生し、大きな課題となってきました。
神奈川県では、これまでもさまざまな取組を行ってきましたが、令和7年4月から福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課内に「災害福祉グループ」を新設して、さらなる取組を進めています。
今回は国の法律改正の動きと、本県における災害福祉の取組について、皆さまにご紹介いたします。
令和7年災害救助法の改正による「福祉サービスの提供」の追加
国は災害発生前から発生後まで、国や地方自治体などの各機関の対応について「災害対策基本法」等の法律において定めています。
一方「災害救助法」は災害発生後の被災者の「救助」と「生活支援」に焦点があてられており、救助の種類に避難所の設置や、医療および助産の提供などが定められていますが、令和6年1月に発生した能登半島地震から得られた教訓を今後に生かし、災害対策の強化を図るため、令和7年7月の法改正により、新たに「福祉サービスの提供」が位置付けられました。
内閣府の災害救助事務取扱要領においては「福祉サービスの提供」の範囲として、災害時要配慮者に関する「情報の把握」「相談対応」「避難生活上の支援」「避難所への誘導」「福祉避難所の設置」と定められています。
これまでも災害時には、国からの通知に基づいて、福祉支援が実施されてきましたが、今回の法改正により「福祉サービスの提供」が位置付けられるとともに、災害時に福祉サービスの提供を担う活動に対する経費も災害救助費として位置付けられました。法律に位置付けられたということは、被災地で福祉支援が円滑に行われるよう求められているということでもあります。
「かながわ災害福祉広域支援ネットワーク」と「神奈川DWAT」
これまで県では、大規模災害の発生に備え、福祉関係団体等と協働し、大規模災害時に要配慮者を支援するため、平成28年7月に「かながわ災害福祉広域支援ネットワーク」を構築しました。連絡会を年3回程度開催し、構成団体・自治体(県、指定都市)・事務局(神奈川県社協)の間で情報共有や意見交換などを行っています。
また、大規模災害時に、一般避難所等における要配慮者の福祉ニーズに的確に対応し、避難中の生活機能低下等の防止を図りつつ、一日でも早く安定的な日常生活へと移行できるよう、必要な支援を行う福祉専門職等で構成する「神奈川県災害派遣福祉チーム」(以下、神奈川DWAT)を設置しています。
令和7年9月時点で、社会福祉士や介護福祉士、ケアマネジャー、理学療法士など330名の専門職がチーム員に登録しています。能登半島地震では、神奈川DWATとして初めて被災地での活動を行い、金沢市および輪島市に合計21名を派遣し、避難者のアセスメント、避難生活後の支援調整、なんでも相談窓口での対応などの支援を行いました。
神奈川DWATでは発災に備えて訓練を重ねるとともに、多くの方にDWATを知っていただきたいと考えています。今年は川崎市、平塚市が主催する避難所の運営訓練において、神奈川DWATチーム員登録者が、避難者役への聞き取りを踏まえたアセスメントおよび支援検討を行う訓練を実施しました。
また、DWATの重要な役割として、一般避難所での生活が困難な方を福祉避難所へ誘導するためのスクリーニングがあります。その際には、福祉避難所がどのような場所であり、どのような環境であるかを知っておくことが大切になります。そのため、今年度神奈川DWATは、県立茅ケ崎支援学校の福祉避難所資機材組立訓練に初めて参加し、教職員との情報交換を実施しました。

茅ケ崎支援学校での訓練のようす
避難行動要配慮者名簿と個別避難計画
災害時に速やかに避難するためには、事前の備えが重要です。個別避難計画(以下、計画)は、例えば「どの経路でどこに避難するか」「誰が避難を支援するか」「どのような配慮が必要か」などをあらかじめ決めておき、スムーズに避難するための計画です。
災害対策基本法により、市町村では地域防災計画において避難行動要支援者(災害時に自ら避難することが困難で、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援を要する方)の範囲を定めて、名簿を作成することが義務となっています。市町村によって避難行動要支援者の範囲は異なりますが「障害者手帳の等級/要介護度/1人暮らしをしている」などが基準になります。
そして、避難行動要支援者名簿に載っている方のうち、計画作成に同意した方を対象に作成します。
本県は令和7年4月時点で、県内市町村の計画作成率が2・2%と、全国最下位となっており、作成が進んでいないことが課題となっています。一方で、令和6年台風10号発生時には二宮町で計画を作成していた方が、速やかに避難をすることができたなど、計画作成が実際の避難行動に繋がった事例も生まれています。
県では、これまで防災・福祉の担当職員による市町村の個別訪問、定期的な市町村担当者会議の開催など、市町村の計画作成を支援してきました。今後も、県と市町村との情報共有等を密に行いながら、課題の解決に向けて取組を進めていきます。
県内ではケアマネジャーや相談支援専門員などの福祉専門職や民生委員・児童委員などが協力して計画作成のサポートを行っている自治体もあります。計画の作成に向けて、皆さまのご協力をお願いします。
福祉避難所
福祉避難所は、高齢者や障がい者など、要配慮者のために、バリアフリー化され、多目的トイレなどが整備された社会福祉施設等を利用して開設される避難所です。
一般の避難所は、段差や狭い空間、騒音など、要配慮者にとって生活が困難な環境となることがあります。県では市町村担当者会議を毎年開催するなど、市町村の福祉避難所の設置や体制整備を促進しています。
市町村によって異なりますが、福祉避難所が、災害発生直後から開設される例は少なく、まずは地域の小中学校の体育館や公民館等の避難所に避難し、その後、要配慮者を福祉避難所へ誘導する流れを、多くの市町村が想定しています。
令和6年11月時点で、県内の指定福祉避難所は156カ所、福祉施設等と協定を締結などしている福祉避難所が1647カ所あります。
しかし、実際に福祉避難所の開設・運営訓練をしたことがないというところも多いのが実情です。県では今年度、福祉避難所の開設訓練を支援する事業を実施して、災害時に速やかに福祉避難所を開設・運営できるように支援しています。

平塚市での福祉避難所訓練のようす
おわりに
災害は、いつ起きるかわかりません。まずは、自らの命を守る「自助」が大切であり、自らの積極的な取組が不可欠です。そして「共助」として、平時から地域における互いの顔の見える関係づくりが、災害時の速やかな避難行動や助け合いに繋がっていきます。さらに「公助」として避難所の開設や福祉サービスの提供などが行われます。
県地域福祉課災害福祉グループでは、さまざまな施策を庁内外で横断的に推進し、多様な方々と顔の見える関係をつくりながら、災害時に誰ひとり取り残さない福祉を目指して取組を進めていきます。(県地域福祉課災害福祉グループ)