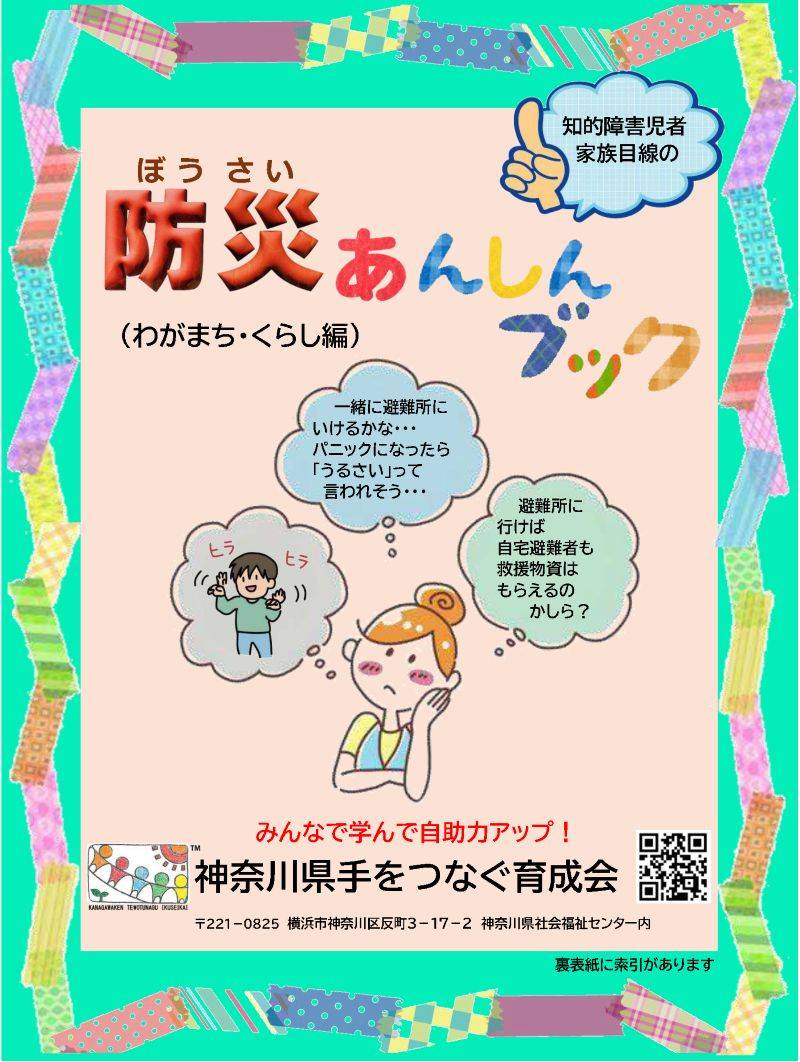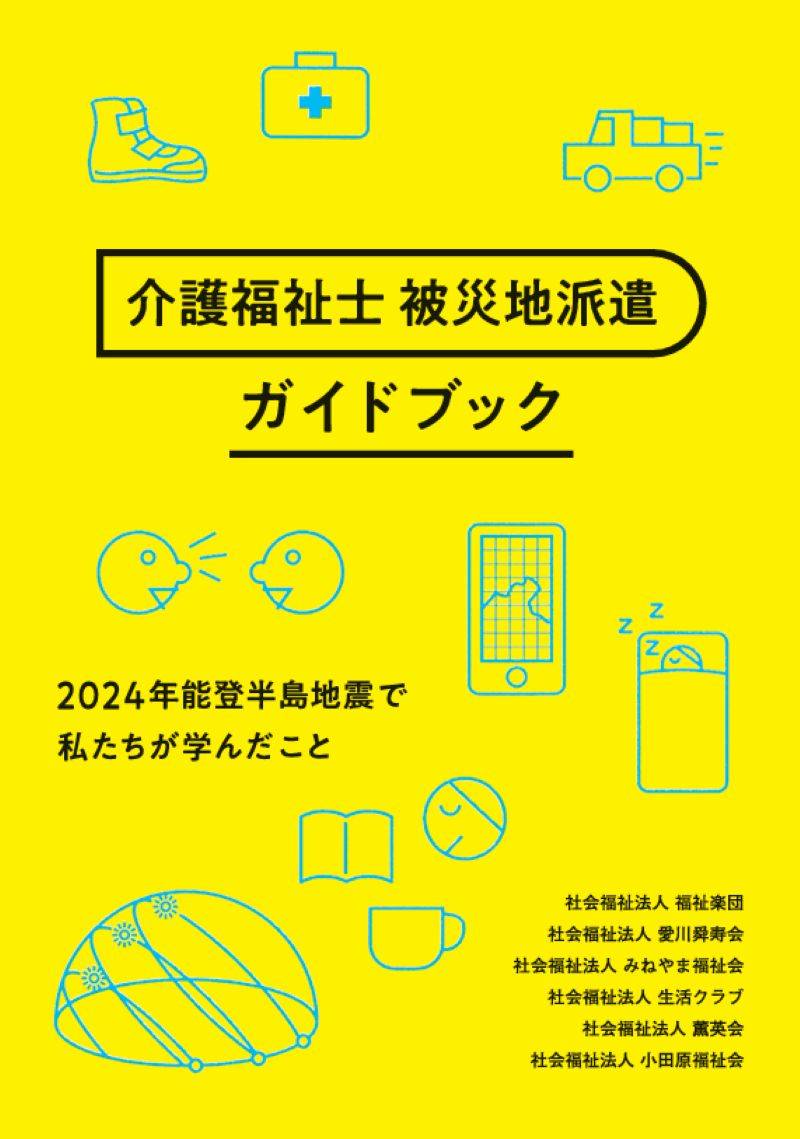災害時にもアレルギー患者が安心できる社会へ
アレルギーを考える母の会
- 分野 その他の活動分野 /
- エリア全国 /
- 推進主体 民間団体(NPO等) /

アレルギーを考える母の会は平成11年に発足し、同20年のNPO法人化を経て活動は26年目を迎えました。年間400人ほどから寄せられる相談に応じ、健康回復をサポートする活動を中心に、患者が適切な医療を知り自ら治療に取り組み自己管理を可能にするための講演会・学習懇談会活動、患者を支える社会の仕組みづくりを働きかける調査・研究、提言活動などを続けています。
当会は平成23年3月に発生した東日本大震災から被災地での活動に取り組んでいます。きっかけは以前から連携していた、阪神淡路大震災で被災した兵庫県西宮市在住の女性の「母の会は被災地に行かないのか」という一言でした。その言葉に背中を押され、手探り状態でしたが4月7日、ようやく通れるようになった東北自動車道を経由して仙台市に向かいました。到着した日の深夜に震度6強の余震に見舞われ、翌日向かった沿岸部の惨状や、静まり返った避難所の光景を今も鮮明に覚えています。
被災地での活動は、食物アレルギーやアトピー性皮膚炎、喘息などアレルギーの病気を理由に、避難所での生活に困っている人がいることを、避難所運営などに携わる方々に理解してもらうことから始まりました。必要性が理解されない活動は、かえって迷惑とされかねません。岩手、宮城、福島3県の沿岸部の自治体などを、時に原発周辺は大きく迂回しながら訪ね歩き、3巡目の訪問のころから、ようやく本気で話を聞いていただけるようになりました。
被災地で活動を開始した当初、避難所などを訪れて分かったことがありました。最前線では保健師、栄養士、看護師の役割が大きく、避難所では保健師がキーマンでした。加えて被災した方々にとっては、見知らぬ人による支援ではなく日ごろ身近にいる人からの支援が安心できることも痛感しました。従って被災地での当会の活動は、主に被災自治体の職員を応援することを中心としました。具体的には市町村などの支援担当と連携し、患者サポートに必要な情報や資材を提供、訪問した避難所では患者をサポートする体制づくりに協力し、併せて直接連携できる患者をサポートすることにしました。その後、被災1年を経過するころからは、保健師など専門職の方々に研修機会を提供する活動に比重を移しました。費用は当会が用意し、アレルギー専門医を同行して行った研修会は130回を超え、研修を実施した市町との連携は今も続いています。熊本地震(平成28年)や西日本豪雨(平成30年)、北海道胆振東部地震(平成30年)など令和6年能登半島地震まで、こうした協力を続けています。

平成30年9月4日、倉敷市真備町 薗小学校の避難所での活動のようす
災害時のアレルギー患者支援は、東日本大震災の反省から始まったと言っても過言ではありません。当時、現地で見聞きした実情は「ある食べ物を『アレルギーがあるので食べられない』と言ったら『こんな時に贅沢を言うな』と避難所の担当者に怒られた」「アトピー性皮膚炎が伝染すると思われ、避難所を出なければならなかった」などというものでした。当会はこうした実情を厚生労働省の担当課などに訴え続けました。
東日本大震災発生から2年後の平成25年、多くの課題を背景に災害対策基本法が改正され「高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要するもの(以下「要配慮者」という)に対する防災上必要な措置に関する事項」が規定されました。
そして、これと併行して作成が進められた「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」(内閣府防災担当、平成25年)に、初めてアレルギー患者への配慮が盛り込まれました(表)。国に実情を訴え続けた当会も策定の検討会に加わり、アレルギー学会などと連携して要望した内容が盛り込まれました。
「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」内閣府(防災担当)平成25年8月、同28年4月改定(抜粋)
その後も厚生労働省の「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針」(平成29年)では、アレルギー対応食材やミルクの備蓄、自治体の防災部門と保健部門の連携推進などがうたわれました。令和4年には、国の最も重要な計画である「防災基本計画」にも「被災地方公共団体は、避難所における食物アレルギーを有する者のニーズの把握やアセスメントの実施、食物アレルギーに配慮した食料の確保等に努めること」が明記されるなど、取り組み方針の整備は着実に進んでいきました。
一方、災害への備えや避難所運営などの実務は主に市町村が担い、支援内容も市町村の裁量に任されています。当会が研究協力者として参加した「大規模災害におけるアレルギー疾患患者の問題の把握とその解決に向けた研究」(厚生労働科学研究、令和2・3年度)で、「避難所で食物アレルギーを有する避難者に配慮した準備をしていますか」との調査に対し、「準備している」と回答した自治体は38%、アレルギー対応食品の備蓄数量や備蓄場所などについて住民に情報公開している自治体は13%にとどまっていました。当会が活動してきた被災地でも、少しずつ取り組みが進んできているとはいえ、実感は調査結果と一致していました。引き続き、国の指針などに沿った自治体による災害への「備え」の充実が求められます。
令和6年能登半島地震の被災地で活動する中、被災半年後の7月に、特に被害が大きかった輪島市、珠洲市、七尾市、能登町、穴水町、志賀町を対象に、前出「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」の取り組み状況について調査を行いました。調査対象の6市町のうち3自治体がアレルギー対応食を備蓄し、1自治体がアレルギー対応ミルクを備蓄していました。そしてこれまでなかった取り組みとして、すべての市町の避難所などでアレルギー患者のアセスメントが行われていました。調査に寄せられたコメントにも「備蓄食料はすべて28品目(加工食品で表示が義務付け、または表示が推奨されている原材料)を不使用としていた。しかしアレルギー患者を把握する方法や対応の基本に対策がなされていなかったため、避難所ごとの対応にバラつきが出てしまった」など、これまでなかった意識の高まりが伺われたのは、反省点であるとは言え大変にありがたく思いました。ありのままの実情を報告していただいた6市町には、心から感謝しています。

令和6年6月11日、輪島市内での活動のようす
今後、アレルギー患者支援という視点でも福祉関係者との連携が広がると考えています。理由の一つは平成25年の災害対策基本法改正の目的に沿い、神奈川県も含めた自治体で、避難の支援にとどまらず他の「食」に脆弱な方々とともに食物アレルギー患者も「要配慮者」として支援されるようになることが期待されます。もう一つは今年、法改正により災害対策基本法に「福祉サービスの提供」が明記されたことで、「要配慮者」の多様な支援ニーズに応え、同じ場面で活動するケースが増えるのではないかと思われるからです。
関係者の皆様には、災害時を含む緊急時に提供する食事や炊き出しなどに、国の指針に沿った原材料表示を行い、食物アレルギー患者の安全確保に努めていただけることを願っています。そのためにも、災害時のアレルギー患者への対応について、情報の共有や関係者同士の協議が進むことを期待しています。
(アレルギーを考える母の会)